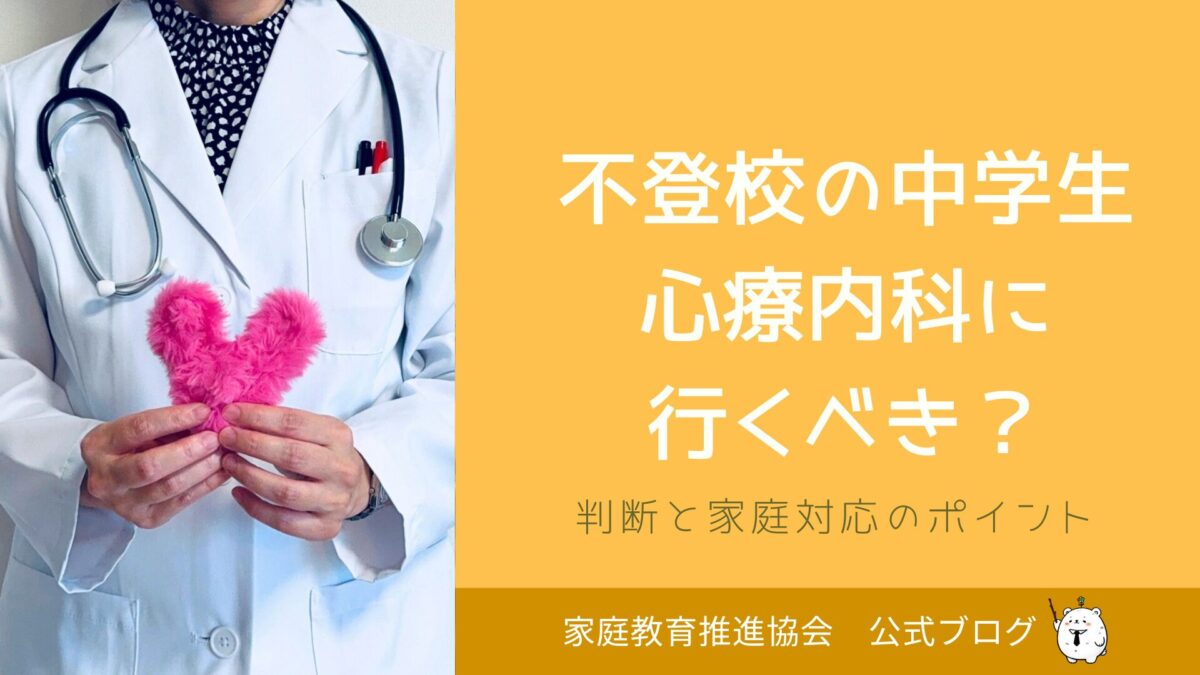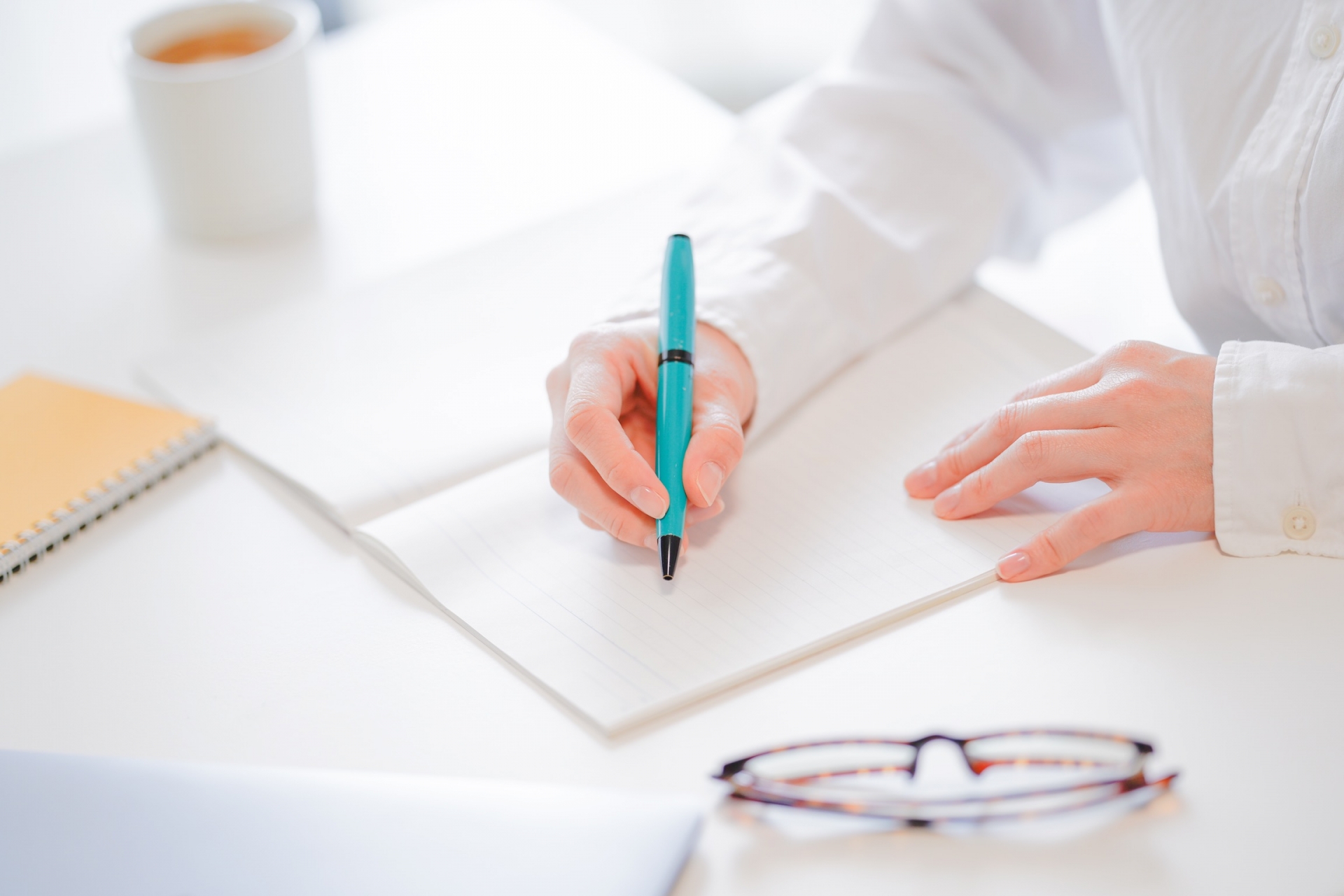「学校に行けない状態が長引いてきた」
「子どもが昼夜逆転している」
「最近、笑わなくなった」
そんな様子を前に、親として「このままで大丈夫なの?」と不安になる瞬間はありませんか。
ネット上では、「不登校は心の休息だから見守ればいい」という言葉もあれば、「早めに心療内科へ行った方がいい」という意見もあります。
どちらが正しいのか、判断に迷ってしまいますよね。
実際、私のもとにも「心療内科に行かせたほうがいいですか?」という相談はよく届きます。しかし、行ったほうがいいケースと、もう少し家庭で見守るべきケースの両方があるのです。
この記事では、不登校支援に10年以上携わってきた公認心理師として、
- 心療内科を検討すべきサイン
- 通院中の家庭での関わり方
- 医療×家庭支援がうまくいった事例
を、心理学の視点からわかりやすく解説します。
「うちの子に今、必要なのは何だろう?」と感じているお母さんが、安心して次の一歩を考えられるよう、丁寧にお伝えしますね。

もし小学生で心療内科をご検討されている方は、当協会と提携しているエンカレッジのブログもお役に立つかもしれません。
>エンカレッジ公式ブログ
「不登校のとき心療内科に行くべきかの見極め方!受診のデメリットとは」
中学生が不登校になったとき、心療内科に行くべき?

「学校に行けなくなった」
「朝になると泣き出してしまう」
親として、どうすればいいか分からなくなる瞬間ですよね。
しかし、不登校=すぐ心療内科に行くべきとは限りません。一方で、医療機関のサポートが必要なケースも確かにあります。
実際に私が支援してきた中学生たちの中でも、「心療内科に行ってよかった」と感じた子もいれば、「特に変わらなかった」と話す子もいました。
違いを分けるのは、行くタイミングと目的の理解です。
詳しくまとめていきますね。
心療内科を検討するべきサインとは
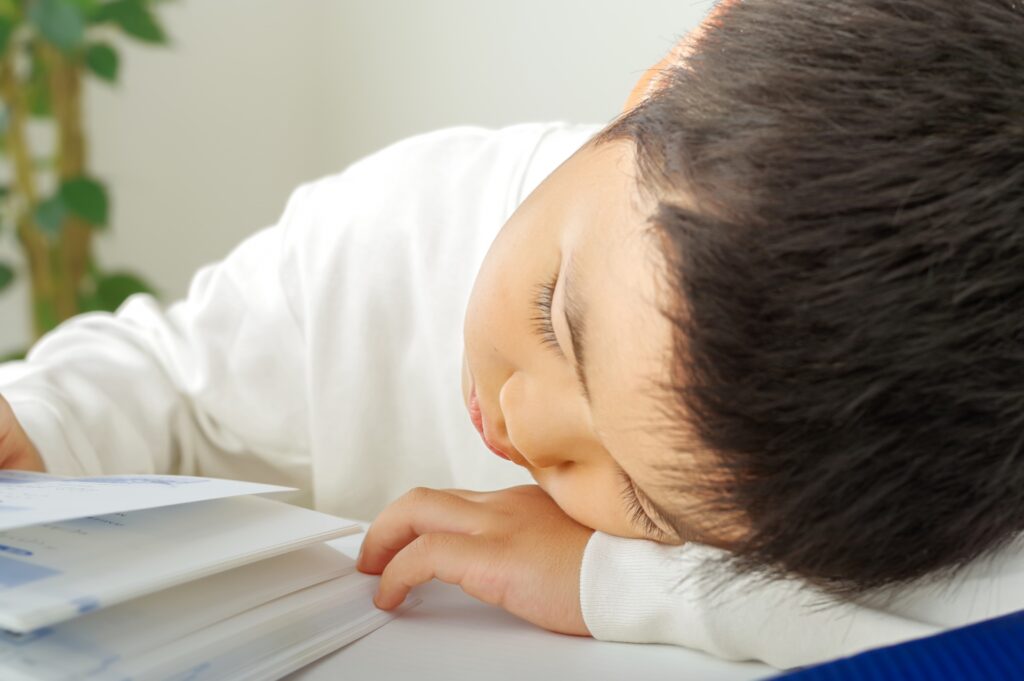
まず、受診を考えた方がいいのは次のようなケースです。
- 食事や睡眠が極端に乱れている
- 「生きていても仕方ない」「消えたい」といった言葉が出ている
- 表情がなく、好きなことにも興味を示さない
- 自傷行為をほのめかす
こうしたサインがあるときは、医療の力を借りる段階です。
心理学では、これを「バーンアウト症候群(燃え尽き)」と呼んだりもします。過度なストレスや無力感が続くことで、心身のエネルギーが枯渇した状態です。
この状態では、本人の意欲だけで立て直すことは難しいのです。
「眠れない」などの身体のSOSを見逃さない

子どもが「もう生きていても、、、」と口にしたとき、親はとてもショックを受けます。しかしその言葉の裏には、「助けて」「分かってほしい」という強い訴えが隠れています。
もしあなたの子どもがそう言ったなら、一度「それほどつらいんだね」と共感を示すことが最優先です。
否定したり、「そんなこと言っちゃダメ」と止めるのではなく、「どうしたの?」と静かに耳を傾けてください。
親が焦って受診させる前に確認すべきポイント

心療内科を受診する前に、次の3つをチェックしてみましょう。
無理矢理ではなく、子どもが「病院へ行ってみたい」と感じているか
病院に行くことで解決するとは限らないと親が認識しているか
家庭でできることを見直してみたか
医療機関は、治す、整理する場所。受診がゴールではありません。
主治医との相性や治療方針も様々なので「利用するものであって、縛られるものではない」という親の認識も大切です。
心療内科に通っている間の家庭内対応のコツ

実際に通院が始まっても、すぐに変化が見られるとは限りません。
「薬を飲んでいるのに変わらない」と焦る親御さんも多いですが、中学生の心療内科では強い薬はほとんど使えません。なので、目に見える変化も起こりにくいのです。
ドクターが重視しているのは、「環境調整」と「安心感の回復」。診断書によって学校から配慮してもらえたり、「薬があるから大丈夫」と安心できたりすることで、徐々に回復を促すというものです。
つまり、心療内科に通っているとはいっても、本当に回復するには家庭での関わりが非常に大切なのです。
ここでは、ご家庭での対応ポイントをまとめていきますね。
医療と家庭の役割を分けて考える

医師の役割は、診断と治療方針の提示。親の役割は、その子に合った日常のリズムを整えること、本当の意味での自信や自己効力感を育てることです。どちらも欠かせませんが、混同してしまうと子どもが混乱します。
「先生がこう言ったから」「薬を飲めば治る」という伝え方ではなく、「安心できる方法を一緒に探そうね」と声をかけましょう。
子どもが「見守られている」と感じられれば、それだけでオキシトシン(安心ホルモン)の分泌が促され、心が落ち着きやすくなります。
抑うつは“心”だけでなく“身体”から来ることもある

心療内科で意外と多いのが、身体的な原因による抑うつ症状です。
甲状腺機能の低下、鉄欠乏性貧血、ホルモンバランスの乱れなど──「心の問題」と思っていたものが、実は体のSOSだったというケースもあります。
体調不良が長く続く場合は、血液検査や内科的診断も並行して行うとよいでしょう。
薬に頼らず、安心材料としての医療連携を

通院が続いても、明確な変化が見られない子も少なくありません。それでも「診てもらっている」という安心感には意味があります。
これは「プラセボ効果(偽薬効果)」と呼ばれる心理現象です。実際の薬効がなくても、「守られている」「効くはず」と期待効果や暗示効果があることで症状が軽減することがあります。
つまり、心療内科は「治す」ためだけでなく、「支える」ための場。
家庭ではその安心をつなぎ、焦らずに日常を積み重ねていくことが何より大切です。
心療内科×家庭教育でうまくいった支援の事例

【ケース①】第三者(医師・カウンセラー)が入ることで整理できた心
中学2年生のAくんは、母親への反発が強く、家では会話が成り立たない状態でした。
しかし、カウンセリングで医師に話すうちに、「自分の気持ちを聞いてもらえた」と感じ、少しずつ心を開き始めました。
やがて家庭でも落ち着いて話せるようになり、母親との関係修復が再登校のきっかけになったのです。
【ケース②】漢方・頓服・カウンセリングで支えられた子どもたち
「薬に頼りたくない」と心配する親も多いですが、心療内科では漢方中心の治療や、必要に応じて頓服(不安が強いときだけ服用)を出すケースもあります。
ある中学生の女子生徒は、「頓服を持っているだけで安心できる」と話していました。
飲まなくても、「持っている」こと自体が支えになるのです。この心理的効果も大切にしたい視点です。
【ケース③】発達特性を理解し、前向きに変わった高校生のケース
高校生になっても不登校が続いていたBくん。
心療内科で検査を受けた結果、軽度のADHD傾向があると分かりました。
医師から診断されたことによって、「忘れっぽい自分が悪い」と責めていた気持ちが、「仕方なかったんだ」と自分を認めるきっかけになり、そして「忘れっぽいから、どう工夫すればいいかな」と考える等気持ちが前向きに変化していきました。
やがてメモ活用や音声入力など自分なりの工夫を始め、少しずつ登校できるようになりました。
このように、心療内科は「薬に頼る場所」ではなく、本人の理解と環境調整を進めるパートナーなのです。
「不登校の中学生、心療内科に行くべき?判断と家庭対応のポイント」まとめ

不登校の中学生に心療内科をすすめるかどうかは、「睡眠・食事の乱れ」「死にたいなどの発言」があるかどうかがひとつの判断基準です。
ただし、心療内科は“治療の最終手段”ではなく、安心を得るための選択肢でもあります。
薬を飲むことが目的ではなく、「一人で抱え込まなくていい」と子どもが感じること。それこそが、回復の第一歩です。
親としてできるのは、医療に委ねすぎず、「あなたのペースで大丈夫」と伝え、子どもの変化を観察し続けること。
心療内科と家庭がチームになって支えていくことで、再登校への道はきっと見えてきます。諦めずに行動して行きましょう!
「心療内科に行くべきか」「どう家庭内で対応して良いか」などご不安な方は、当協会の初回無料カウンセリングもご活用くださいね。