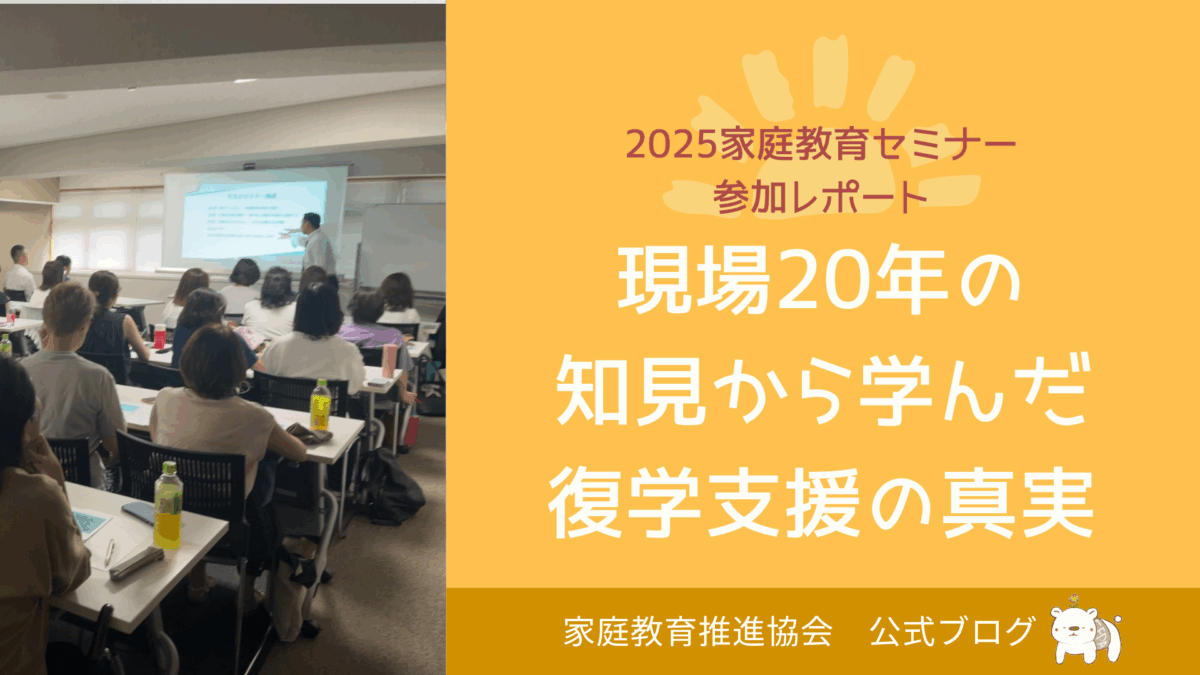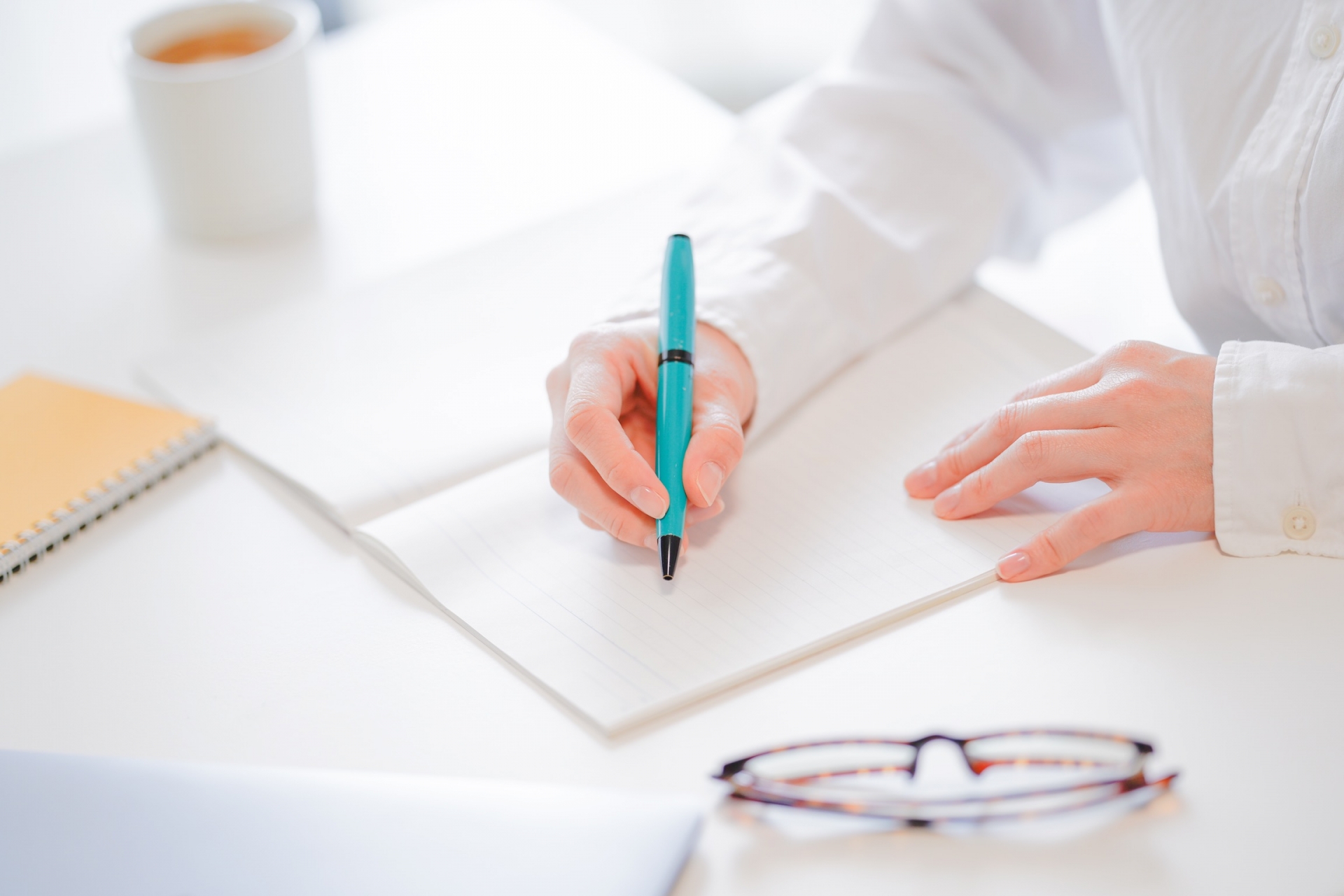7月に大阪、8月に東京で開催された「2025家庭教育セミナー」では、藤本先生が 20年以上の現場経験から初めて語る復学支援の真実 をテーマに、熱のこもった講演を行いました。
会場は満席となり、アンケートでは 79.5%の方が「満足」と回答。

参加者の皆さんの関心の高さが伝わってきますが、今回はセミナーの様子を少しご紹介しますね!
テーマは「見守り論争」

SNSでも話題の、不登校の「見守り論争」「介入論争」。
「このまま休ませていいのか?」「親が動くべきなのか?」──多くの家庭が今まさに迷い続けているかと思います。
そこで今回のセミナーでは、次のポイントを実例を交えて整理しました。
- 見守ることと介入することの本当の意味
- 各支援機関の特徴と違い
- 再登校に向けて家庭でできる準備
皆さん、とても真剣にメモを取りながら受講されていました。

皆さんの熱心な様子を見て、主催した私たちも嬉しく感じました。
参加者の声

藤本先生の20年以上の経験で得た知見を詰め込んだ今回の家庭教育セミナー。
ご参加いただいた方々からは、こんなお声を頂きました。
「見守り方や関わり方の参考になった」
「介入の必要性について納得できた」
「今後の家庭での対応のヒントになった」
「支援機関の違いがよくわかった」
印象に残った学びとしては、次のような声が多く寄せられました。
- 不登校の再発を想定して対応する必要があると知れた
- 親のタイプ×子のタイプが448通りあると聞いて驚いた
子どもが不登校になるとどうしていいかわからない親御さんがほとんどだと思いますが、こうして1つ1つ学んでいこうとする姿勢は子どもを想うからこそ。
ぜひ、今回のセミナーで学んだことをご家庭で役立ててほしいと思います!
懇親会で広がったつながり

セミナー後には懇親会も開催されました。
同じ悩みを持つ保護者同士がざっくばらんに話し合う場となり、以下のようなご意見を多数いただきました!
- 「不登校のことを安心して話せる場所があった」
- 「同じ思いをしている人が他にもいるとわかって気持ちが軽くなった」
不登校になって子ども本人は辛いと思いますが、実は子ども以上に親御さんが思い悩んでいることもとても多いので、このようなリラックスした雰囲気で交流できる時間は、 参加者にとって大きな励みになったようです。
まとめ

不登校や登校しぶりへの対応は、家庭だけで抱えるにはとても難しいテーマです。
だからこそ、現場で積み重ねられてきた知見を学ぶこと、同じ立場の仲間とつながることが、次の一歩を踏み出す力につながります。
「不登校の会は不安…」と感じる方も多いと思いますが、実際に参加された方の多くが、 「話してよかった」「一人じゃないと思えた」 と安心して帰られました。
もし迷っている方がいたら、ぜひ一度参加してみてください。
学びと安心、そして新しいつながりを得られる場になるはずです。
次回のご案内

9月の夏休み明けは、不登校が増える時期と言われています。
そんな悩みを抱える親御さんを対象にした 「家庭教育相談士によるお話会・懇親会」を 9/21(日)に開催します。
どうぞお楽しみに!
次回お話会の詳細のご案内と申込フォームはこちら↓になります!